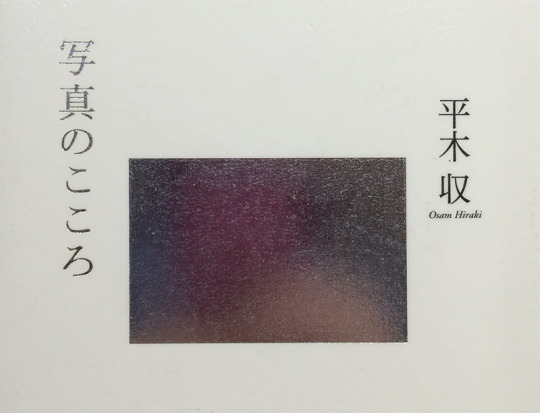
平木収氏はつくば写真美術館の6人のキュレーターの一人で、2009年に他界されました。同美術館についての研究本「1985/写真がアートになったとき」を読んで、金子隆一氏が平木氏について熱く語っていたのが心に残り、本書についても紹介されていて、読みたくなりました。
本書は平木氏が生前発表した数多くの文章の一部をまとめたものですが、編集委員会によるあとがきにあるように、
つねに社会へと開かれようとしたその評論の魅力を一冊の本として伝えたいという周囲の願いから、本書の計画が持ち上がった。過去の文章をただ網羅するのではなく、これから写真を学ぼうとする人たちを含め、幅広い層の人たちに写真の楽しさと奥深さを知るきっかけを提供できるよう、本人が残した単著の構想メモをベースに全体の構成と掲載内容が検討された。
という編集になっており、私のような写真について知りたい、学びたいと思う人にとっては心強い参考書になりました。印象的なところ、参考になったところを書き留めておきます。
第一章「見つめる楽しみ」では、写真の味わい方を料理の味わい方を例にしての説明が度々出てきますが、それらがとても判りやすく、また、以下の文章に、ハッとさせられました。
写真のおいしい味わい方の定石としては、柔軟に素直に、そしてすでに頭の中に溜めてあるイメージをすぐに取り出せるようにして、それらを重ね合わせたり対照したりしながら、気楽かつ真剣に見ること
どんな味なんだろうとワクワクしながら料理に臨むように、どんな展示なんだろうとワクワクしながら写真展に望んでいるだろうか?そのように臨むこともあるけれど、私の場合、ちゃんと見なきゃとか、元取らなきゃとか、身につけなきゃとか、余計なことが心を占めている場合も少なくないです。
第二章「写真を学ぶために」にまとめられた文章は、写真前史を含めた写真の沿革、写真史上の名マニフェストを引き合いに出しながら写真の誕生から今日までの動向の説明、フォトジャーナリズム、平木氏が提案した『フィログラフィー(画像学といった意味合い)』という考え方などから成っています。時系列ではない写真の歴史、諸問題や考察が解説されていて、個人的には、写真史の教科書というよりも、教科書よりも面白い副読本という印象を持ちました。
このような構成は、直接的には本書の編集委員会によるものかもしれませんが、結果的に、『写真史も1980年代に写真表現以上に変化を見せた現場である[*1]』と指摘する平木氏の説に則った体裁になっている、と思ってしまうのです。
この章で大きく取り上げられている、ロバート・フランクの「アメリカ人」や、1966年の写真展「Contemporary Photographers Toward a Social Landscape」のキュレーターであるネイサン・ライオンズがカタログテキストとして著したマニフェスト「社会的景観に向かって」は、ちゃんと読みたいと思いました。「社会的景観に向かって」は、カタログテキストでありながら、主眼となるものは、写真界の現状を打破することに向けられていたようです。平木氏によるマニフェスト要約を引用しておきます。
写真家の仕事とは、おのおのの文脈の中で理解されるべきものなのだが、「現実とは何か」「美とは何か」という概念の押し付けが先行し、写真をしかつめらしい何々派に分けてしまって、必要な意見の交流を妨げてきた。思えば写真ほど人間の文化を率直に反映できたものはかつてなく、写真の登場で造形芸術の世界もその成り立ちが変わった。写真は人間に体験の広がりをもたらしたのだ。事態は変わりつつあるので、古びた風景感を払拭して、例えば「人間と人間、そして人間と自然の連環」といった相互性を中味とする風景感を新たに打ち立てるべきだ。
「社会的景観に向かって」という提言は新たな一派を成そうという意図のものではないことと、状況と景観の概念がその必要に応じて許容量を増して行かねばならず、さもなければ大局的な見地から、時代を直視できなくなる、ということ。その文脈に沿って写真のことを考えると、かつてのドキュメンタリーとかスナップとかリアリズムといった分類やレッテルの貼り付けは、用語のごった煮で、誤解、勘違いをごまかす手管のようなものだ。問題は、事物や事情がどうなっているのかという疑問を抱き続けている写真家が、意識的にせよそうでないにせよ、写真という手段を、それを用いる十分な根拠を持って用いてゆくことだろうということである。人間の諸状態の真意を汲み取ることのできる写真、そこに向かうべきである。
今年はこのマニフェストから50年目に当たりますが、初めて目にした私としては、込められた決意の重さに只事ではない何かを感じると同時に、コンテンポラリーとは、イコール「現代」と安直に思っていた自分が恥ずかしくなりました。
同じく第二章にある、ジャーナリズムについての文章では、最後にピューリッツァー賞について触れています。以下の締めの言葉は重く受け止めたいです。
顕彰という儀式的なパフォーマンスを通じて社会におけるジャーナリズムの役割を再認識させること。ジャーナリズムというシステムそのものが人間の社会生活の常軌を維持する装置であるべきで、そこをジャーナリストも読者も共通認識としようではないか、というマニフェストこそ、ピューリッツァー賞の意味するところである。
第三章「展覧会の現場から」は、アサヒカメラに連載された展評のいくつかですが、これは見てみたかった!と思ったのが、「荒木経惟・飯田鉄・高梨豊『住んでみたい街』」。これは、都市をとることでは定評のある写真家を擁して、各界の著名人に住んでみたい街を訪ねてもらい、著名人と街を写真に収めるという企画ということで、平木氏曰く『著名人よりも強い個性が前面に立っていた荒木経惟』、『著名人と周波数があっていた飯田鉄』、『著名人と正対して向き合って、なおかつ目前の都市間を押し出す高梨豊』と論じられていて、どうしても気になってしまいました。
なお、この展示は住宅情報誌に連載された企画から生まれたもので、「私だけの東京散歩」(作品社刊 下町・都心篇、山の手・郊外篇の二分冊)にまとめられていることを知りました。今度読んでみようと思っています。
また、本書にマン・レイが脇役的に登場する章が二箇所ありました。私は展示を見てもマン・レイがかつて生きていた人と実感できなかったのですが、平木氏が紹介したエピソードを読むことで、こんな一面もあったのかと輪郭が見えてきたような気がしました。このような、『また聞き』オーラルヒストリーを知ることができるのも嬉しいですね。大変面白い内容でしたが、興味のある人はぜひ本書を読んでみてください。
————
[*1]
従来、写真史とは、時系列に技術が進歩、発展してきたかをたどる仕事であったが、そうではない手法で、その変容(改革)を企てた何人かの人物や機関があったとのこと。
例えば、アメリカ人写真史家ユージニア・パリー・ジャニス「フランス・カロタイプの芸術」では、写真術が市民社会に入って行く時代に居合わせた人物たちの人となりで、文献や資料から往時の写真と社会と個人の関係を物語風に綴り、人間が写真を用いるようになったことの意味、驚き、悦びをしたためている、という。