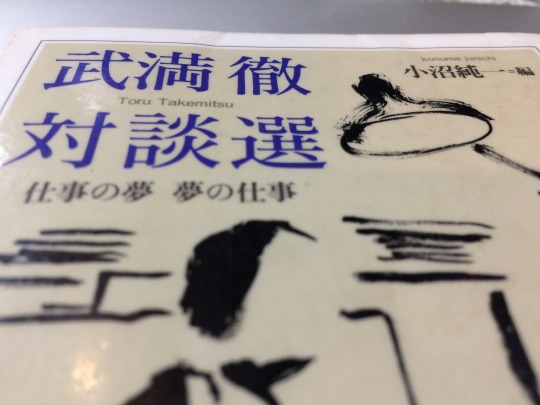
東京国立近代美術館で展覧会開催中の吉増剛造、その名前をインターネットで検索していたときに見つけた本。展示の予習にと思い図書館で借りてみましたが、目次を見て驚きました、対談する方々がバラエティーに富んでいて。キース・ジャレットはやや意外だけど、デビッド・シルビアン、大竹伸朗はえ!?という感じ。趣味が広く浅く雑食系な人は面白いと思える本です。
人選だけではなく、対談中に出てくる昔のエピソードも猪突猛進で微笑ましい感じです。冒頭の「徹子の部屋」!?に武満徹が出演した際に語った17歳の頃のエピソード<日比谷公会堂の演奏会を見たいけどお金がないという旨を事務所の人に言ったら入れてくれて、演奏会の後に作曲の早坂文雄をつかまえて感想を伝えた>からは、あの痩せている見た目からは想像ができないバイタリティーを感じました。他の対談でご自身が語っていましたが常に理想主義的な立場で物事に向かっていた、そんな姿勢がこのエピソードからもうかがい知れる気がしました。
デザイナー・杉浦康平との対談では、二人ともインドネシアに訪問してガムランに触れる機会があり、<日本全体がヨーロッパの近代をお手本にして、北半球という一枚の巨大な鏡に向かっていった。近代の芸術のあり方は、基盤は厚いところに”天才”が突出して文化を進めて変えていった。その際に自分の仕事を普遍化、記号化していくこととなる。一方インドネシアでは色々なところで色々な人が音楽をやっている(金属的な打楽器が多く、近代日本で伝統的な楽器よりも演奏が容易ではあるものの)。生活と分かち難く行き来している。音階もどんどん生まれてくる>というような意見が交わされていました。芸術と芸能の違いだと言ってしまえばそうなのかもしれませんが、楽器が弾けない、絵が描けないと思っている人(私もその一人かもしれませんが)は、芸術的な物差しでしか測ってはいけないと思う恐れから生まれるのかもしれない、と思いました。
個人的にはキース・ジャレットとの対談に耳が痛い思いをしました。<うっかりすると即興が単に自分を繰り返し模倣する自己模倣に陥ってしまう>など、即興に留まらず制作全般に言えるのではないでしょうか。また、キース・ジャレットが<何という詩人がいったのかは知らないのだけれど、私の好きな一節に”the more personal the statement is, the universal it is”(主張がパーソナルであればあるほど、それはユニバーサルなのだ)というのがあります>と言っていて、覚えておきたいと思いました。パーソナルと大体同義だと思っていますが、自分にとって身近でないと(=身近にならないと)人に伝えることはできない、そんな風に思うことがあります。
展覧会予習のために、吉増剛造との対談についても覚え書きします。「声の魔」について、それが立ち現れる瞬間というのはあるわけなのかと尋ねた際の吉増剛造の答え<予想もしないところからその音の魔のようなものが現れてきて、その魔の手にひかれてゆくようなところってある。(略)詩を書くときに速度が自分にとって問題で、スピードアップをしないと詩はでてこないという固定観念があって、間を詰めることによって、それこそマジックの魔がでてくるものです>、それを聞いて武満徹が返したのが<邦楽の演奏家たちも間を言いますが、いまいましく思うのは間は大事なんだけど、間の中に自分が吹いたり叩いたりした音よりももっとたくさんの音を感じさせるだけの音というのがなくて、ひたすらただ形の上で間を作るということが。(略)大事なのは速度感だと思うのです。いまや間を開けることはとてもやさしいのだけれど、間を詰めることの方がむずかしい>。
大竹伸朗との対談は、1992年に雑誌に掲載されたものですが、二人とも海外でも仕事をされていて、海外でのCDジャケットやポスターがアーティストの意向にそぐわないことが多いという話が驚いたとともに面白かったです。武満徹の<自分の音楽とまるで違う装いで(ジャケットが)出されるとやっぱりガックリくる。外国でプレスされると外国で独自のデザインをして出すのだけど、舞妓さんの後ろ姿と遠くに富士山が影みたいにあって、びっくりした。フランス人の若い作曲家たちは、なにを怒っているんだという。自分たちのレコードもこんなきれいなジャケットで出たらいい、いつも抽象的な幾何学模様みたいなものばかりで出されているという。あのときはカルチャーショックというか、分かり合うまでには時間がかかると思った>に対して、大竹伸朗は<去年のアメリカのグループ展ポスターも芸者テイストで、商店街などの街灯の飾りにするプラスチック製の桜が入っていて、出品作家の彫刻と組み合わせて舞妓さんの後ろ姿がだぶっている。(略)グループ展全員の作品が日本的なものをモチーフにという人はだれもいなかったが、お客さんを美術館に呼ぶには、舞妓さんと桜と富士山が必要というか、武満さんのお話の時代から全然変わっていない。フジヤマ、ゲイシャ以後の日本を理解している人も20年前と比べればたくさん出てきていると思うが、一般にアピールする段階になると何もなかったかのようにスッと戻る>。24年後の今はどうなのでしょう?
ジョン・ケージ(きのこの話、エッチング:マルセル・デュシャンの線の記憶によって銅板の上に糸を落とす。「停止原基」?)、ヤニス・クセナキス(ポリトープ、ユピック)との対談も覚えておきたいですが、最後に掲載されている、1982年の黛敏郎、岩城宏之との対話では、核について議論などもあり、仲のよい間柄だからこそ、こういうことも普通に言えるのかもしれませんが、では、今日私が仲のよい人と議論できるかというとどうなんだろう?など考えさせられました(むしろ意見の違う人とはお互いに疎遠になろうとするのではないかと)。